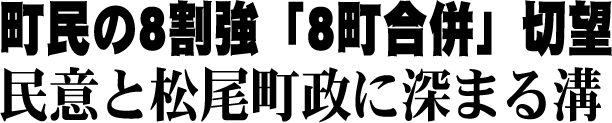
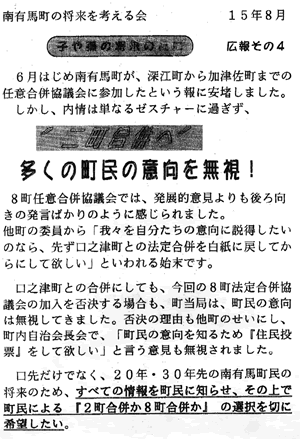 |
| このチラシが町民不在政治の全てを物語る、町民を目覚めさせた告発書。 |
住民投票は73%の投票率でしかも広域合併を望んだ人が3,162人、2町合併を望んだ人が614人と8割強の人が町が薦めてきた方針にNOを示したことになる。如何に民意が見えない政治を続けてきたかという証左である。
町側は、住民投票を開催するにあたっても、条例に「投票率が50%を割ったら開票されない」という姑息な規定を盛り込んだり、議員を中心に「住民投票には法的拘束力は無いので行っても無駄」というような話をするものもいたらしいが、一生に一度か二度しか出会わない変革の時を、住民はしっかり見つめ判断した、ということだろう。
8町合併を支持した人も必ずしも8町合併がベストとは思っていないだろう。深江や布津町とは殆ど交流もなかったろうし、生活習慣や経済圏も異なる。その線引きのむずかしさに不安が残るのも事実だろう。
しかし、残された道が8町か2町かの選択しかなかった住民からすれば、国や県がハッキリと「2町が合併してやっていける時代ではない」と公言している以上、どこで線を引くかよりも、取り残される不安を払拭する方法を選択せざるを得なかったのだろう。現に県は6町に対して重点支援地域に指定する方向で検討を始め、逆に2町については重点支援地域指定を保留するという、見せしめ的裁量権を発揮している。
「流れ」とはこういうものである。誰かが(国や県を含めて)意図的に作るものなのか、自然発生するものなのか分からないが、一気呵成に決着がついたりする。ついこないだまで、6町だったり4町だったり、2町合併もあり得た。
流れは完全に8町合併推進
2町側は町としての実績に慢心して少し驕りがあったのだろう。町と民意の乖離、目付け役を果たせない議会、町対町の駆け引き、国や県の意向、それらが激しく絡み合う中で、風の流れを見誤ったのだろう。バブル時代、護送船団方式や談合を繰り返し、温く温くと我が世の春を謳歌してきた銀行や建設業の姿に似てやしないか。他方現在の勝組は外国との競合を繰り返し、早くからリストラを断行してきた自動車業界やソニーを始めとした、常に技術革新を目指して世界の流れ、時代の流れを先読み、努力してきた企業である。
これだけの大差が付けば町も住民の意向を無視することはできないだろう。議会も同じである。流れは完全に8町合併推進に決定した以上、今度は6町へ合併参加への「お願い」に行かねばならない立場へと変わって来る。
6町側が言う「合流は歓迎だが、論議にブレーキをかけ続けた2町に対して、感情的なしこりは残る。2町の法定協を解散した上で協議に臨んでもらわなければ、待たされた側の住民に説明がつかない」との尤もらしい意見もまた住民にかこつけた自分達のメンツだけで、この際南有馬町、口之津町を分断し、7位、8位の立場に置いてしまおうという戦略がミエミエである。
何処の町も、殆ど住民は参加していない。町と議会で話が進められ、不満はあっても決まったことに従うのが住民の立場であり、日本人の習性なのである。都合のいい時だけ「住民の意向」だとか「住民に説明がつかない」とか使うのは首長や議会の常套句なのである。
南有馬町が苦しい立場に追いやられたのは事実である。最終的には天の声もあり、8町合併で決定するだろうが、当分は6町側が牽制も含めてブツブツ言うだろう。しかし、こちら側に失敗もあったわけだからこうなった以上、忍の一字で合併参加をお願いするしかなかろう。加津佐という飛び地もあるし、県や国が8町合併を望んでいる以上、参加拒否はあり得ない。相手側には2町に対して、ペナルティーかお灸をすえたい、という気持ちもあろうが、議論を戦わすことや拒否権は当然の行使だから、そのことで何ら臆することはないが、2町とも住民と一体でなかったことが決定的な弱みになるだろう。寧ろ最初から8町合併を訴えて立候補した井上氏が町長になってた方が、6町側としてはすんなり受け入れ易かったろう。ここは皮肉の1つも言いたい6町側にチョッとガス抜きをさせて8町合併後、堂々と論戦を張ればいい。
本来なら南有馬町議会は解散し、信を問わなければならない程の失策をしたことになるが、幸いリコール運動も出ていないようだし最長の場合でも1年半しか任期のない議員の立場を理解し、いたずらに町政に混乱と空白を作ってはいけない、という住民の配慮と親切的暖かさだろう。この住民の気持ちを町長や議会は裏切ってはいけないのである。過去はしっかり反省して頂くとして、これからが大切なのである。
松尾町長も思わぬ重き荷物を背負わされ当分はこの問題に振り回されて大変だろうが、これが町を代表する本来の首長の姿である訳だからへこたれずに頑張って頂きたい。また図書館建設にしても、8町合併が決定した後でなければ、当紙が指摘する通り、箱物としての図書館は建っても2年後の新書を購入する予算や維持、管理費を賄うことはできないだろう。やはり住民の意向をよく聞いてから建設に着手すべきである。
特に議員団は住民が8町か2町かで苦難の選択で悩んでいる際中に「下水道」の視察という名目で、わざわざ2泊3日で群馬まで出掛けたらしいが、下水道の視察だけなら県下でも充分視察可能な場所はあるだろうに…、何でそんな無駄使いをしなければならないのか。
最初から「旅行ありき」がミエミエである。猛省を促したい。
〔以下次号〕
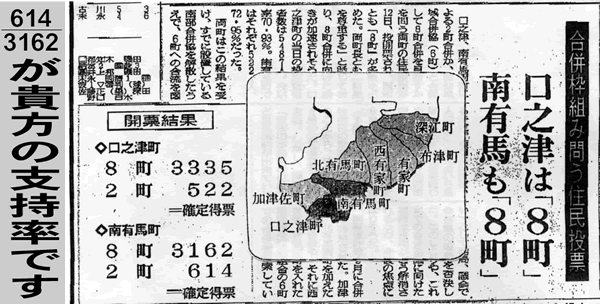 |
| これでも、まだ2町合併を推しますか?松尾町長 |
| ©2005 敬天新聞社
info@keiten.net |