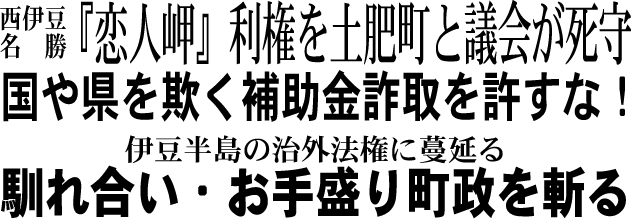
 |
「好きな人の名前を唱えながら鐘を3回鳴らすと結ばれる」という言い伝えも今は昔。最近じゃ利権欲しさに権力者が鐘を鳴らしまくるという『恋人岬』 |
年間23万人の観光客が訪れる西伊豆最大の景勝地『土肥町恋人岬』がその原因だという。先ずは恋人岬について説明しよう。
恋人岬に施設が造られたのは、今から21年前の昭和58年。眼下には紺碧の駿河湾、遠くに御前崎や富士山を望み、大海原の彼方には“土肥町名物”の「美しい夕日」がゆっくりと沈んでいく、そんな絶景が自慢の観光スポットだ。
この建設事業には町の予算もつぎ込まれたのだが、当然の事ながら、町だけでその莫大な事業費を賄えるはずなど無く、国や県からの補助金・起債(借金)に頼りながら事業が進められた。また恋人岬とその付帯施設の管理運営業務は、昭和58年の設立以来、町から委託を受けた同町観光協会が行なってきた…。
と思っていたのだが、ここにはあるトリックが仕掛けられていた。実は、管理運営を行なっていたのは観光協会ではなく、土肥温泉旅館協同組合(以下「旅館組合」という)だったのである。
恋人岬の開業当時、地方自治法第244条の2③は「公の施設管理」について次のように定めていた。
「…(前略)…その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる」
この条文によると土肥町は、恋人岬施設の管理運営業務を旅館組合に委託することが出来ない。何故ならば、旅館組合は単なる任意団体であって土肥町からの出資も受けていなければ、況してや公共団体でも公共的団体でも無いからだ。だからこそ表向きは、町が公共団体である観光協会に管理を任せているかのような“体裁”を繕って来たのである。しかし、何故そこまでして“裏”で旅館組合が管理運営を行う必要があったのか?
それは、一部の人間の利益を優先させた結果であった。
本来、恋人岬で上がった利益は全て、管理運営を行って(いるかのように見せかけて)きた観光協会に入っていなければならなかった。しかも公共団体である観光協会は、その利益を町の様々な催し物を開くなどして町民に広く還元すべき立場にあった。
ところが、実際にはそれらのカネが陰の管理運営者である旅館組合の手に渡っていたのだ。単なる任意団体に過ぎない旅館組合には利益を還元する義務など無いから、長年にわたって本来の利益享受者ではない旅館組合だけが潤ってきたことになる。
もちろん、旅館組合だって一銭も出さずに利益だけを取っていた訳ではない。
恋人岬建設費用の一部に当たる約4,000万円を三島信用金庫・土肥支店から借り入れ、「寄付金」という形で町に納めている。
町としても、国や県に対して「町の事業」という形を取って補助金を受け取った手前、旅館組合のカネまで受け取ったとなると、費用の“二重取り”との批判は免れまい。それがきっかけで、「実は旅館組合に管理運営を任せていた」ということまでバレたりしたら大問題である。
従って寄付金という形ぐらいしか受け取る理由が無かったのだろう。聞くところによると、町はそのカネを歳入して国への起債返還に充てた模様だ。
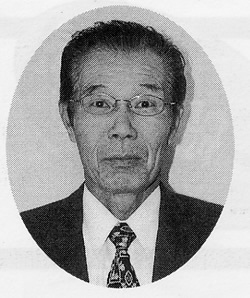 |
「町長が良いって言えば審議はいらねぇヅラ」。土肥町が誇る超凡議長=勝呂宗夫大先生
|
何れにしてもここで問題となるのは、恋人岬には町は勿論のこと国や県からのカネも注がれているという点だ。このカネは「土肥町(自治体)が行なう地域振興に役立てる」という前提で交付された“公”のカネである。結果的に観光名所となって地域振興に役立ったとしても、所詮は旅館のオヤジの寄り集まりである民間組織がその利益を享受しているのであり、国や県が当初からそのことを知っていたとしたら、そもそも補助金を交付する訳などあるまい。
極言すると土肥町は、民間事業を公共事業と偽って国や県から補助金を騙し取ったことになり、地方自治法に反する形態での管理運営を行なってきた、ということになる。
しかし、この欺瞞に満ちた馴れ合い町政を長年にわたって続けてきたツケが、皮肉にも合併によって回ってくることになる。それは旅館組合と恋人岬との蜜月関係の終焉である。
恋人岬の施設建設費の一部=4,000万円を『寄付金』という名目で町に納めた旅館組合には、施設の所有権移転、またはそれに対する抵当権の設定などが出来ない。つまり、表向き「土肥町の施設」という形を取って来た以上、合併後は当然伊豆市の施設ということになり、伊豆市が同観光協会に管理運営を委託したら、旅館組合には何も残らないことになるのだ。
彼等にしてみれば、借金までして造った施設が自分の物にもならない、管理運営業務にもタッチできないとなると、正に“踏んだり蹴ったり”だろう。今まで毎年自分達のものだった利益が、合併後には全く入って来なくなる。
そこで、土肥町議会は昨年の3月、定例議会に於いて「土肥町恋人岬の関連施設及び管理に関する条例」(以下「恋人岬条例」)という条例を可決した。この条例の中身を端的に言うと、任意団体だった旅館組合を公共的団体と位置付け、今後は恋人岬の管理運営を旅館組合に任せよう(本当は初めから旅館組合に任せてたけど…)というものだ。
そもそも旅館のオヤジの寄り集まりに過ぎない民間組織を、町議会で「公共的団体」と位置付けてしまうその神経を疑わずにはいられないが、実はここに特筆しておくべきことが、もう1つある。
恋人岬条例が可決された約3ヶ月後の昨年6月13日、公の施設管理について定めている地方自治法第244条の2③が、次のように改正された(平成15年6月13日公布、9月2日施行)。
「…(前略)…法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる」
つまり、公共施設の管理を行なう団体は、土肥町が指定する団体ならば公共団体か民間かを問わない、というルールに改正されたのだ。これなら民間の団体である旅館組合でも、町が指定さえすれば管理を任せられることになる。何も慌てて恋人岬条例など通さなくても、今年の合併には充分間に合ったのだ。
ところが、土肥町が取った行動はそれとは正反対のものだった。即ち「民間に出来る事は民間に」ではなく、単なる民間団体を無理矢理公共的団体に仕立て上げ「利益を特定の団体に」誘導する法案を、審議も行わずに僅か1分ほどで可決したのである。
だいたい、旅館組合が公共的団体だというなら、恋人岬の施設が出来た昭和58年に、なぜ町議会でそのことを審議しなかったのか。旅館組合は昭和22年から活動していた筈だ。そうすれば、何も20年以上にわたって地方自治法に反する形での管理運営を行わずに済んだし、国や県を欺いて補助金を詐取した、ということにもならずに済んだのだ。
平成15年に出来て昭和58年に出来ない理由は何処にも無い。ということは「当時の担当者や町長、町議はみんな馬鹿だった」ということが、図らずも町役場の現職員、現町長、現町議の行動によって露呈した、と解釈すべきか…。
それに「町議の中に旅館組合員が存在する」という事実も見逃せない。地元町民の皆さんにとっては既に常識だが、土肥町では古くから旅館経営者が町会議員を務める例が少なくなかった。十数名の町議のうち必ず数名は旅館経営者だったといっても過言ではない。旅館経営者ということは、もちろん旅館組合に所属しているわけだ。
即ち、頭の中では旅館経営者(組合員)として恋人岬事業の損得を勘定しながら、表面では町議の顔をして法案に賛成することが可能なのだ。同じ方法で、施設の管理運営を表向きは観光協会に委託、裏では旅館組合が行なうことも、そして合併前に旅館組合を公共的団体として位置付けておくことも、何でも出来てしまうのである。こういうのを日本語で“お手盛り”という。
恋人岬条例に関する本紙取材に対し、町会議長=勝呂宗夫が議会事務局を通じて寄せた回答が、町政の体質を如実に物語っている。
曰く『町長が認可を下したので審議をしなかったと思う』。このご様子だと議会制民主主義の意味さえ理解できているか疑わしい。議長をしてこの体たらくだから、何をか言わんや。
合併後の7ヶ月間は、現在の4町の全議員=57名が伊豆市議を務めるそうだが(その後、初選挙で26名に減る)、記念すべき初代伊豆市議をこんな天才(?)どもに任せていては、伊豆市の将来は、広々と遠くまで見渡せる恋人岬の「パノラマ」とは対照的に「お先真っ暗?」だ。
(以下次号)
| ©2005 敬天新聞社
info@keiten.net |