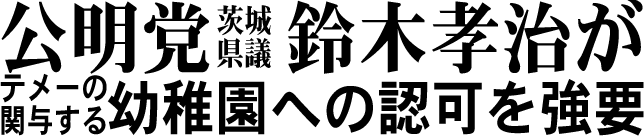
|
|
無認可保育園というと、『経営優先の杜撰な保育』といったイメージを抱く方が多いかもしれない。昨今では働くお母さんが増えた事もあって、保育ビジネス業界も様々なアイディアを用いた業者が鎬を削っている。しかし利益を優先させると保育料は高額になり、逆に低料金で勝負しようとすればどこかでコスト削減を迫られるのは自明だ。
平成13年に乳児死亡事故を起こした「ちびっこ園池袋西」などは、1つのベビーベッドに2人の乳児を寝かせ、保育士の人数を極端に少なくするという営利至上主義が“窒息死”という惨事を招いた。他人様から預かった大切な生命を守れないのだから、ビジネス以前の問題である。
但し、ここで断っておかねばならない事は、無認可とはいっても、中にはもう何十年も地域の人達に愛され続けてきた(認可が無いだけの)善良な保育園だってあるということだ。まずは「無認可」という言葉に対する先入観を払拭して読み進んで頂きたい。
現在、茨城県には300以上の無認可保育園がある。公明党茨城県議・鈴木孝治が理事予定者に名を連ねる無認可保育園『ひまわり保育園』(以下「ヒマワリ」という)=飯田和子園長=もその中の1つだ(無認可の幼稚園は「園」の名称が使えないため、現在は『ひまわり幼稚舎』として営業中。また本紙先月号の予告を見て慌てたのか、早速“闇の紳士”への依頼もあったとか…)。
その所在地、茨城県東茨城郡常北町には認可を受けた保育園3つ、公立幼稚園1つ、しかも殆んどがヒマワリからそう遠くない場所にある。無認可のヒマワリとしては苦しい立場であろう。無認可保育ビジネスが激戦区でも凌いで行けるのは、やはり大都市の繁華街など「子供を高額で預けてでも働きたい保護者がいるエリア」という要因が不可欠と思われるからだ。
認可保育園や公立幼稚園を凌駕出来るようなアイディアは無いか?普通なら託児時間を延長するとか、給食を他所より充実した健康メニューにするなど考えるだろう。しかし、鈴木の選んだ方針はそんな可愛気のある物ではなかった。さすが折伏団体の政治家、県や町に難癖を付けて、無認可保育園をいきなり3年制の幼稚園に格上げしろと凄んだのである。
平成13年、ヒマワリは阿久津勝紀・常北町長(当時)に対して認可を申し入れた。「子供の未来を考える会」なる団体が集めたという、『ヒマワリを3年制の幼稚園に格上げする要望書』と、2,000名以上もの署名を携えての申請だった。
学会の人海戦術の凄みを見せつけた形となった。
町長が諮問機関に調査・意見を求めた結果、常北町では少子化が進み既存の公立幼稚園・認可保育園でさえ定員割れを起こしている状態で、新たな認可を出しても単なる『共倒れ』になろう事が分かった。
認可を受けたい一心のヒマワリにしてみれば駄目で元々だろう。しかし、他の園にしてみれば『共倒れ』は平穏な生活権の侵害だ。行政としてはそのような状況を招く訳にはいかない。
町長は熟慮の末、諮問機関の出した調査結果を尊重し、ヒマワリからの申請を断った。
すると鈴木は橋本昌・茨城県知事に対して、予算委員会の場で圧力をかけるという行動に出た。予算委員会の数日前、読売新聞茨城版(平成13年12月12日付)に『3年保育幼稚園移行活動に逆風・署名2,000人超だが…町長諮問機関が反対』との見出しで、ヒマワリに関する記事が掲載された。
内容は、ヒマワリと常北町民が悲願する「3年制幼稚園」の認可申請に町長側が反対し、皆ガッカリしているといったものだ。ここでは『反対』という言葉が使われている。恐ろしい事だが、これは完全に鈴木の側に立った記事である。
町長は反対したのではない。正当な行政法の様式に則って公共の福祉を大前提に判断しただけだ。そして、ヒマワリが「他人の権利を侵害」する事が無いよう計らっただけなのだ。しかし憲法も行政行為も、ひとたび公明党の手にかかったら(都合のいい時は利用して)差別・弾圧になってしまうようである。
鈴木は、その新聞記事を持って予算委員会に赴き、マスコミ(といっても地元版だけなのに)も県民も懇願してる、早くヒマワリの幼稚園認可を出せ、と言わんばかりの論調で県側に詰め寄った。
 |
太作君(あっゴメン、大作とか名乗ってたっけ?)、君の教育がなっとらんから、こんな勘違い男が出てくるんだよ
|
茨城では昭和40年代、幼稚園・保育園の競合で保育施設が共倒れにも似た状況に陥った事があった。子供の多かった40年代にである。現在ではその教訓を踏まえ、地方自治の原則に基づいて地元の状況を当該行政に精査させ、安全と判断した上でしか認可を出さない方針を取っている。いくら公明党がギャーギャー騒いでも、駄目なものは駄目なのだ。
その県の方針を鈴木は批難した。しかし、知事としては「他の県内300の無認可園の事は知らねぇ、俺んトコどうにかしろ!」と鈴木に言われて「ハイ、公明党様の仰せの通りでございま〜す!」とは答えられないのだ。いちいち議員のコネや圧力に屈していたんでは、県政は成り立たない。
当時の予算委員会の席では知事は即答を避けた。しかし、今なお鈴木の強面談判は続いている。
現在、常北町政は当時の公明の圧力に屈しなかった阿久津前町長から、三村孝信町長へと引き継がれている。二千名以上もの署名で「新たな幼稚園を熱望している」という常北町の、現実の児童数は以下の通り。
3歳児109人、2歳児107人、1歳児102人、0歳児はナント96人(2桁)。子供は確実に減り続けている。
茨城県知事・橋本昌殿、不当な圧力に負けて、将来常北町が「昭和40年代の失政の二の舞いになる」事だけは回避して戴きたい。もし、本当に3年制幼稚園を町民の大半が望んでいるのなら、まともな公立幼稚園を3年制にすべきだ。3年教育を望む町民にしてみれば、公立の(安い)園料の方がありがたいに違いない。
公明党議員・鈴木孝治の頭にあるのは県内の他の認可外保育園の健全運営や、常北町の児童の教育云々では無い。色々と御託を並べて策を弄してはいるが、結局は自分が理事を務める予定の幼稚舎の、認可という「看板」が欲しいだけなのだ。繰り返すが、0歳児は100人以下だ。
鈴木による、党の強大な票田と金権力の威光を笠に着た暴挙は枚挙に暇が無いが、紙面の都合上、次号に譲るとしよう。
鈴木に関する情報をお持ちの方は、本紙までご一報を!
(つづく)
| ©2005 敬天新聞社
info@keiten.net |
